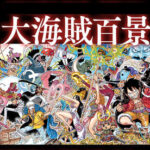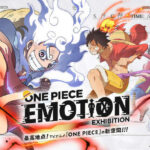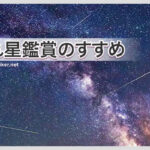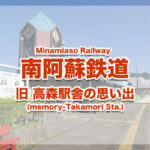前回の『Roadhouseの仕様・部品構成』では、パンクに備えてホイールに適合するバルブ長の予備チューブを準備しました。
チューブレスタイヤでないなら、走行前に予備チューブ確認・準備は重要なことです。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1122-624x416-1.jpg)
今回の試走で使うタイヤの空気圧【3ber】は、フィッティングの時と同じ。装着されるタイヤは[Schwalbe S-One]で推奨エア圧は【3.5〜5.5ber】です。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2015/11/1118-13-624x416-1-300x200.jpg)
エア圧が低いとパンクの可能性が高くなりますが、このタイヤの場合、少し低めでギャップを通過しても、まだ安全マージンがあると感じました。もちろん、ギャップを通過するときは抜重をしています。あと、ライダーの体重【私は56kgくらい】という要素もあるので一概に言えないのですが。
| グリーンハウス | 液晶スマートテレビ(チューナーレス) ゲーミングPCモニター |
|---|---|
 | |
実走:舗装路・砂利道
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-2-300x200.jpg)
さて、エア圧調整が済んだところで『Roadhouse(ロードハウス)』発進です!
注意書きのステッカーを剥がし忘れている…
加速/巡航/登坂
スリック系のタイヤを履いたバイクは、アウターチェーリングからの漕ぎだしも軽やか…と言いたいところですが、鉄フレームは2kg近い重量があるため、ある程度漕ぎだしは重い。ここは意識してペダリングする必要があります。
スピードが乗ってくると巡航スピードは維持しやすい。一般的な向かい風でも、とくに気になることなく前進します。このように、平地を走る場合は「鉄素材だから」という意識は薄いでしょう。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-3-624x416-1-300x200.jpg)
しかし、坂道にさしかかって傾斜が上がってくると、スチールフレームであることを教えてくれる重量に重力が掛かり始めます。斜度の高い登坂では、ペダリング入力を考えずに変速していると、いつの間にか一番軽いギアのインナーロー[インナー34t、ロー32t]で走行しています。
私は貧脚なのでパワーもトルクが低いです。でも、同じルートをシクロクロス『GIANT TCX 0』のインナーロー[インナー36t、ロー30t]より意識的に入力しないと速度は落ちていきます。もちろん、シクロクロスのタイヤはブロックタイヤです。
また、ダンジングで加速する場合、カーボンフレームだとフレームの存在を忘れてしまいそうになりますが、このスチールフレームだと意識しなくてもフレームの存在を教えてくれます。
| 天然生活 | みかど本舗 : 長崎カステラ 切り落とし(1kgセット) |
|---|---|
 | |
乗り心地/振動吸収性
スチールチューブを選ぶユーザーのほとんどが、鉄ならではの振動吸収性や乗り心地に期待してクロモリチューブバイクを求めていると思います。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-4-624x416-1-300x200.jpg)
Roadhouseは、イギリスのチューブメーカ『Reynolds(レイノルズ)853』を採用しています。このチューブは軽量で耐久性が高いことで有名。このバイクはスポーツ指向に振られたグラベルロードバイクなので、この軽量スチールを選択したのでしょう。
個人的には、Reynolds 853は硬いチューブだと思っています。
実際に砂利道をそれなりのスピードで走行すれば、衝撃の高い振動はライダーに届きます。ただ、衝撃のエッヂ部分をある程度丸めて伝わる感じになります。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-5-200x300.jpg)
このバイクで大きく振動吸収しているのはカーボン製のフロントフォークです。衝撃の対象物を乗り越えても、うまい感じに緩和してくれます。これはグラベルロードバイクにとって重要なこと。
フロントとは対照的でリア周りは剛性が高く、鉄フレームらしい『しなり』を明確に感じていません。もっと実走を増やせば、そういった点に気付けるかも。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-6-624x416-1-300x200.jpg)
次に衝撃吸収してくれるのが30cのタイヤ。こちらのエア圧【3ber】ですが、もう少し落として【2.8ber】あたりで支障がなければ、より衝撃吸収対策ができそうです。
ホイールの振動吸収性についても観察しているのですが、まだフィーリングがイマイチつかめていません。要チェックな項目です。
| Apple | Apple Watch 新品❗️Amazonポイント付与⭐️ |
|---|---|
 | |
ハンドリング
この項目が一番難しい。まだ走行距離が短く、体験したフィールド少ないからです。気付いた範囲で書いていきます。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-7-200x300.jpg)
今言えるとすれば、非常に扱いやすいハンドリングです。コーナーの切り返しでも軽快なヒラリ感はありますがシビアな面は控えています。
例えば、ターマック(舗装路)コーナーでバイクの倒し込みが安心してできる事。また、グラベル(砂利道)コーナーでも急な挙動で振られる事はありません。スライドが緩やかなところもポイントが高い。
ハンドリングは、タイヤによっても随分変わるので、すでに交換するタイヤの検討に入っています。サイドノブが付いたオールロード用や、ブロックパターンのシクロクロス用のタイヤで、走破性やグリップの変化を確認したいです。
タイヤ
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2015/11/1118-624x416-1-300x200.jpg)
標準タイヤの[Schwalbe S-One 30c]は、グリップ面のスリットパターンがほぼスリックで、グラベルロード用のタイヤとしては非常に頼りなくみえます。しかし、オンロードでのスポーツ性能を備えたグラベルロードバイクとしての方向性を考えたら、このタイヤの選択は理にかなっています。
また、タイヤの見た目とは裏腹に、砂利道を高速巡航させても、直進安定性はそこそこシッカリしています。砂利が大きくなるとタイヤの接地性が失われはじめますが、そのまま走ってもコーナー以外で破綻を起こす事はないでしょう。
ただ、グリップ表面にある丸形ノブが非常に低く、短い寿命や摩耗によるグリップ低下が気になるところです。

さて、とりあえず実走して感じた事を並べてみました。まだ書かないとイケナイ事がたくさんあるでしょうが、Roadhouseとの付き合いは始まったばかり。また気付いたら情報を追加していきます。
| 煙神 | 煙神チーズセット : メーカー公式ストア |
|---|---|
 | |
実走:オフロード
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1122-624x416-1.jpg)
前項目では、ほぼ平地のターマック(舗装路)とグラベル(砂利道)を走行しましたが、今回はラフな路面を実走したレビューです。普通のロードバイクなら通過しないルートになります。
走行フィールドは、阿蘇外輪山の林道をメインに、ダートロードから、落ち枝が散乱する土の路面など。傾斜は高いところでは10%強くらいです。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-2-200x300.jpg)
さて、走り出す前にタイヤ[Schwalbe S-One]の空気圧を変更します。納車の頃の空気圧はだいたい【3bar(推奨値3.5~5.5bar)】。ところが、もう少しエアを落としてもオンロード走行には支障がなさそうなので【2.8bar】くらいの設定で走ります。変更する理由は、タイヤのグリップ面積を広げることと、衝撃吸収の向上を狙っています。
| アースコンシャス | エプソムソルト : 自然派入浴剤 メーカー直営店 |
|---|---|
 | |
ダートロード
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-3-300x200.jpg)
外輪山へ上がっていく林道ルートは、無数の木に覆われているため落ち枝が多く、路面には直径数センチの枝が散乱します。落ち枝には更に枝があり、その部分が折れて多数のトゲになります。この部分を踏み抜くとMTBのタイヤでもパンクしてしまうので、なるべく枝を避けて走行。それでも、路面一面が落ち枝の場合はリスクが少なそうな部分を通過します。こうなってくると、パンクするしないは運しだいです。
この辺りの路面は舗装されておらず、日光が届きにくいこともあって路面は濡れた状態が多い。また、若干マディな箇所も多数あります。そんな路面でもタイヤは意志に反して蛇行することなく進んでくれます。
斜面の登坂
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-4-300x200.jpg)
10%強の傾斜があるポイントでは、ギアをインナーロー[インナー34t、ロー32t]に落とし、立ち漕ぎを多めに登坂。ときおり湿った葉や枝に乗り上げるとリアタイヤがスリップしそうになりますが、その辺りは重心とペダリングトルクをコントロールすると上手く通過できます。
こういった路面を低速で上がれるのが新しい[Shimano 105]のポイント。このドライブ系のインナーローは、貧脚ライダーには有難いものです。
なだらかな土の路面
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-5-300x200.jpg)
斜度の高いポイントを上がりきると、広めのフラットトラックへ進みます。ちょっと路面はフカフカ気味なのですが、ペダリングに対してもバイクは軽快に進む。こういった路面は起伏の間隔が大きいことから、Reynolds 853フレームも同調したように良いしなりをしてくれます。またエアボリュームのあるタイヤの接地面も増えるのでクッション性は良好。
| 文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
|---|---|
 | |
砂利大きめのグラベルロード
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-6-200x300.jpg)
ジワジワと標高が上がってくると再びグラベル化していきます。路面の左側は拳より大きく先の尖った石、右側は普通の砂利ですが厚みがあります。
まずは左側からタイヤを載せていきますが、上り坂なのを含め速度は徐行スピード。石の尖った部分にタイヤを載せないようにしていますが、そういった石が散乱しているので結局は踏んでいるようです。多分こういった路面でも、タイヤ構造に組み込まれたプロテクションがパンクのリスクを減らしていると思います。
タイヤのグリップは、石のエッヂにガッチリと掛かるのでペダリングした分は進みます。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-200x300.jpg)
次に道の右側、厚みのある砂利を走行。前後のタイヤを捕られがちになりますが、このルートをMTBで走っても同じ状態なので、ここは仕方がありません。ペダリングに対してロスがあるものの、漕げばノタノタと前進していきます。
砂利道の下りでは、速度が上がるにつれてタイヤの接地感が失われます。しかし、フロントフォークがうまく振動吸収するので緊張感は薄いでしょう。ただ、下りの直進はイージーですが、コーナーだと話は別です。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1121-7-1-200x300.jpg)
グラベルルートでのコーナーリングですが、さすがに[Schwalbe S-One]はスリック系のタイヤであるため、速度域によってはグリップは期待できません。コーナーの進入はスローインにするか、片足を出してスライドを楽しむのもありでしょう。
適切なスピードによるコーナーリングはほぼ安定しているので、進みたいルートへ視線を向けましょう。
それと、もう一つコーナーリングでの注意点があります。
ボトムブラケット位置がシクロクロスより低いため、ペダルの接触に注意しましょう。コーナーでバイクが十分に起き上がっていないのにペダリングを始めると、足かペダルが路面に接触して危険です。シクロクロスに慣れたユーザーはご注意ください。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-7-199x300.jpg)
さて、その他のことですが、砂利道ルートをアップダウン含めて走っていると、フレームやホイールへ跳ね石が頻繁に当たります。バイクへの傷が気になるユーザーは覚悟が必要です。もちろん、タイヤのサイドにも傷が入ります。
| ぷるるん姫 | ヘルシースタイル雑炊 : スープ・ゼリー |
|---|---|
 | |
湿り気のあるオフ路面
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-10-300x200.jpg)
次は湿った土の路面。森林の奥深く入ると地面は常に湿り気がある状態。ルートにわたって落ち枝や倒木が腐葉土のようになっててスリッピーな箇所も多い。
道には木の残骸が散乱するポイントもあるので、時にはスタンディング状態でバイクをコントロール必要があります。また、転がる障害物をクリアするために、前後輪を少しアップさせる事もあります。ちなみに、私の体格【約166cm】とバイクのサイズ【size 49cm】が丁度合っているのか、重心を前後させながら抜重するとタイヤが容易に浮きあがります。
Roadhouseは、ライディングポジションが緩やかなジオメトリだから、バイクを左右に振るコントロールがしやすい。また、悪路でもバランスを崩しにくく、障害物を避ける進路変更でも気を遣いません。
ただ、路面の滑り具合によってはペダリング入力のコントロールが必要になります。あと、湿ったコーナーの進入は十分注意しないと、タイヤがグリップを失って転倒しかねません。特に下りのコーナーは要注意です。この辺りはノブ付きのタイヤを装着することでアドバンテージは上がりそうですが過信は禁物。
実走終了とつづき
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1130-9-200x300.jpg)
さて、様々なルートを走り抜け、Roadhouseは山の尾根へ辿り着き空が見えてきました。普通のロードレーサーなら進入を考えもしない路面を走破するグラベルバイクは、ロードサイクリングのあり方に新しい風を吹かせてくれるでしょう。
そうそう、タイヤの空気圧を【2.8bar】に落とした件ですが、衝撃吸収の効果が上がった実感はありましたし、今回のルートではリム打ちの心配もありませんでした。また、オンロードのコーナーリング時に変にヨレる支障もなかったので、しばらくフィーリングを確かめながら、この辺り【2.8~3.0bar】の空気圧で走行を続けてみます。
まだお伝えしなければいけない情報(油圧ディスクブレーキ、新型Shimano 105、ホイール等)もあるのですが、長文になってしまったので、申し訳ありませんが次の機会にお書きいたします。
| 文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
|---|---|
 | |
実走:ホイール評価
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1122-624x416-1.jpg)
Roadhouseに乗っててフィーリングをつかむのに苦労したパーツがホイールセット[Novatech Road 30 Disc Wheelset]です。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-16-300x249.jpg)
なにせ、バイクフレーム強度が高めな設計なため、初めはフレームとホイールどっちの強度が高いのか判断できずレビューが書けませんでした。しかし、最近Roadhouseに集中的に乗れたことで特徴がつかめてきたのです。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-15-300x200.jpg)
答えを先に言えば、このホイールの剛性は高く、見た目そのままディープリムの特性があることが解りました。
| De’Longhi | デロンギ : 全自動コーヒーマシン |
|---|---|
 | |
ホイールの特徴
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-17-300x188.jpg)
ディープリムは、リムハイト(リムの高さ)が30ミリ以上あるリムで、50〜60ミリ以上になると「エアロホイール」とも呼ばれています。
このタイプは、リムの体積が増えホイールの軽量化が難しくなるのですが、ホイールが回るときにリムの重量に慣性がかかるため速度を維持するのが楽になります。
標準ホイールがディープリムと判断できたのは、中速コーナーでバイクを倒して旋回しているとき、ホイールを起こそうとするジャイロ効果が発生したことです。
タイトなS字コーナーを低いスピードで切り返しするときは気になりませんが、コーナーの半径が大きいカーブで速度がのっていると体感しやすいです。また、登坂でペタリングが重く感じていたのはフレーム重量だけでなく、慣性の掛かっていないホイールの抵抗もプラスされていたからでした。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-20-200x300.jpg)
デメリットばかり述べているようですがメリットはあります。それは、グラベル(砂利道)といった転がり抵抗が増える不整地でも、少ないパワーで巡航スピードが維持できること。それと、ターマック(舗装路)でも、少々の向かい風でスピードが落ちることはありません。
ディープリムホイールは、巡航速度を維持しやすい平地走行を得意としたホイールです。欧米のグラベルロードは、日本のように少ない面積で起伏の差が大きくなく、なだらかなルートが多いために、このようなホイールが選択されたのでしょう。
| キハチ | スイーツ・フーズ・ドリンク : メーカー公式ストア |
|---|---|
 | |
ホイールの剛性
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-18-300x203.jpg)
張ってあるスポークの細さから、最初は「雑に使うと折れる?」と思っていましたが、スポークの本数をチェックしてみると、フロントが【24本】、リアが【28本】と、ロード用としては特に少なめということはありません。また、細いスポークでもテンションを高く張ってホイールの変形を減らすことができるようです。ただ、金属疲労で折れる可能性は高くなります。
ホイールの強度は見ため以上に高く、凸凹のあるフラットなシングルトラックを走破しても、数十センチの段差から飛び降りてもホイールの歪みは認められません。特に縦方向の強度は高く、その代償として衝撃吸収性の低さを何度も実感しました。
他には、コーナーリングでホイールを斜めにバンクさせても「たわむ」というイメージが少なく不整地のコーナでも安心感が高いです。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-300x200.jpg)
強度に関する要因はドライブアクスル部分にもあります。フレームとホイールの回転軸は前後スルーアクスル化され、アクスルのねじれ対策と路面追従性を高めています。これによって、走行中にハンドルを左右にこじってもブレの少ない硬さもあります。[Review 4]で走行したダートの下りでも安定している理由の一つがココにあるようです。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/01/0101-19-300x200.jpg)
ということで、都市部での走行が多く道路環境の関係でストップ&ゴーが頻繁なばあい。また、乗り心地が気になるユーザーは、ホイールを自分好みに変更していけば、乗車フィーリングを大きく変えることができます。しかし、そう思いながらも、今のところホイールを換える気はしばらくないかな?
荒れたルートでもホイールが歪まないところは気に入っています。
実走:評価 追加分
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/1122-624x416-1.jpg)
『KONA(コナ)』が新たに開発したグラベルロードバイク『Roadhouse(ロードハウス)』が手元にやってきて2ヶ月が過ぎようとしています。その間には、走行フィーリングやハンドリングを確認しながらフィッティングを済ませ。最近は気軽にサイクリング&ポタリングを楽しめるようになりました。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-14-300x200.jpg)
Roadhouseは、バイクに深い興味がなければ、舗装路のみを走れるロードバイクにしか見えません。しかし、30Cのタイヤ幅と全天候に対応する油圧ディスクブレーキを搭載することで、従来のロードバイクより路面状況を気にかけるシーンは少なくなります。
| U-collection | 高級腕時計アウトレット |
|---|---|
 | |
私は、荒れた路面に恵まれたローカルな地域に生存しているため、その環境を活かしオンロード以外でグラベルロード(オールロード)バイクを走らせます。
グリップや振動吸収を大きく左右するタイヤの空気圧は、約2.7~3.0berの間で設定しています。この日は凸凹のルートを走行するため、タイヤに衝撃吸収を大きく任せたいので低めの約2.7berにしました。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-8-300x200.jpg)
タイヤは[SCHWALBE S-ONE]。このタイヤはパリ〜ルーベの石畳にも適応できるトレッドパターンで、高速巡航のグラベルロード用タイヤとしてもオススメ。
このタイヤ、先日国内でも流通がはじまり、販売価格が11,000円(税別)とお安くはありません。グリップと耐パンク性能に優れ品質は高く、チューブレス対応となっているあたりが価格の理由になるでしょう。Roadhouseには標準装着ですが、これが摩耗したらコスパ高い[Panaracer GravelKing SK]へ変更しようと考えています。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-21-200x300.jpg)
そんな事を考えながらターマック(舗装路)を走行していると、実走ルートは”あぜ道”へ移行していました。ここからは土壌の上に生草と枯れ草のミックスなため、振動や衝撃はあまり気にしなくていい。しかし、大きく凹んだ”くぼみ”が所々にあるため、何もしないで速度を上げてしまうと”くぼみ”の部分で衝撃を受けるか、前輪が跳ね上がってしまう。
ここは時速20キロ未満でいって、くぼみは腕や脚をクッションがわりに、そして身体を前後に移動させてバランスを取りながら走行。不規則な突き上げがプチロデオ感覚で楽しい。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-10-200x300.jpg)
あぜ道をしばらく走ると、農耕地帯を延々と横断するグラベル(砂利道)のルートへ移行。基本的に作業道なので地盤は締まってシッカリとしており砂利も小さめ。このような路面ならグラベルロードの本領発揮で、時速20キロ以上の巡航スピードでバイクは軽快に進む。リムホイールの慣性とタイヤの振動吸収のバランスが良い。MTBと違って容易に高いスピードで距離が稼げ、次々と景色が過ぎ去るサイクリングは壮快。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-22-200x300.jpg)
農耕地帯の”あぜ道”の路面状態は多様で、いろんな走行状態を確認できる。上のようなコースになると、一見は砂利と土のミックス路面だと予想できるが、途中には拳くらいの岩が散乱していたり、排水用のような溝が川に向かって伸びていたりと適度な刺激があり、意外とサドルに腰を下ろすシーンが続かなかったりします。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-24-200x300.jpg)
そうそう、サドルで思い出したのですが、標準装備のKONA製サドルは、長さや幅がシッカリとした面積があり、クッション量はスポーツバイク向けらしく控えめで締まった硬さがある。サドル中央には楕円状の穴と縦方向に溝が施され、股間の圧迫を抑えています。
私は、レーパンが苦手でアウトドアウェア(Mont-BellかColombia)のパンツを愛用してペダリングしていますが、100km未満の走行では痛みなどの問題はなく”おしり”との相性も良いです。いずれサドルがヘタってきたら、愛用の[SDG BEL-AIR]へ変更するでしょう。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-11-300x200.jpg)
さて、農耕地帯を進んでいると、どんどんマイナーな”あぜ道”になってきました。使用頻度の低い作業道は路面が荒れ気味。ぬかるみ対策に拳数個分の岩が散乱するポイントが多数有り、ロードバイクが走れる限度を超えている。しかし、タイヤの耐パンク性能のおかげか、タイヤをカット損傷することもなく通過。こんな路面状況でもガッシリとしたフレームとホイールのタフさは頼もしい。
ただ、ボトムブラケットの高さはロードバイク並みなので、深い轍の盛り上がった部分がペダルと接触します。なので、盛り上がった部分を走行して問題回避。小岩を回避しながらの巡航速度は約10キロくらいに減速してしまった。
後半は路面状況がMTB向けのようになったけど、緊急回避的にそんな路面が走れるグラベルロードの懐の広さを体験できました。
| チーズガーデン | 御用邸チーズケーキ(チーズ洋菓子) |
|---|---|
 | |
Roadhouseは、グラベルロードバイクでは定番のディスクブレーキを搭載しています。私はカンチブレーキ世代のシクロクロスバイクを所有しており、カンチブレーキの制動力に少し不満をもっていました。ところが、近年は専用のミニVブレーキ[TRP CX ミニVブレーキ]などの登場によって高い制動力を得られるようになりました。
そんなところ、グラベルロードバイクを手に入れることになった為、標準装備されるロード用ディスクブレーキに興味津々でした。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-7-300x200.jpg)
Roadhouseが装備するのは油圧制動の[Shimano RS505 Hydraulic]に、ローター径【140ミリ】のディスクローター、ブレーキキャリパーのパッドには「レジンパッド」が採用されています。
このブレーキセットをドライ状態で作動させた場合、いたって普通の制動力が体験できます。この辺りは、未体験だった多くのユーザーが拍子抜けするでしょう。
![グラベルロード インプレ レビュー[KONA Roadhouse]](https://x.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/04/0101-3-300x200.jpg)
油圧ディスクブレーキは、早くからMTBに採用されている技術で”ガツン”とくる制動力が体験できます。しかし、装備されているディスクブレーキに鋭い立ち上がりの制動力はない。要因としては、ディスクローター径が【140ミリ】と小径であることと、レジンパッドの扱いやすい特性の組み合わせから、この制動力やフィーリングがあるのでしょう。
このブレーキセットは、レバーの入力に対してスムーズで素直なストッピングパワーを発揮します。なので、不用意な握り込みでブレーキングしないかぎりは安全でしょう。一度グラベル(砂利道)あたりで急制動のフィーリングに慣れておくと、危険回避の操作でパニックに陥ることが少ないと思います。
ちなみに、雨天時のウェット制動は未体験です。夏頃の通り雨で体験できたらいいですね。